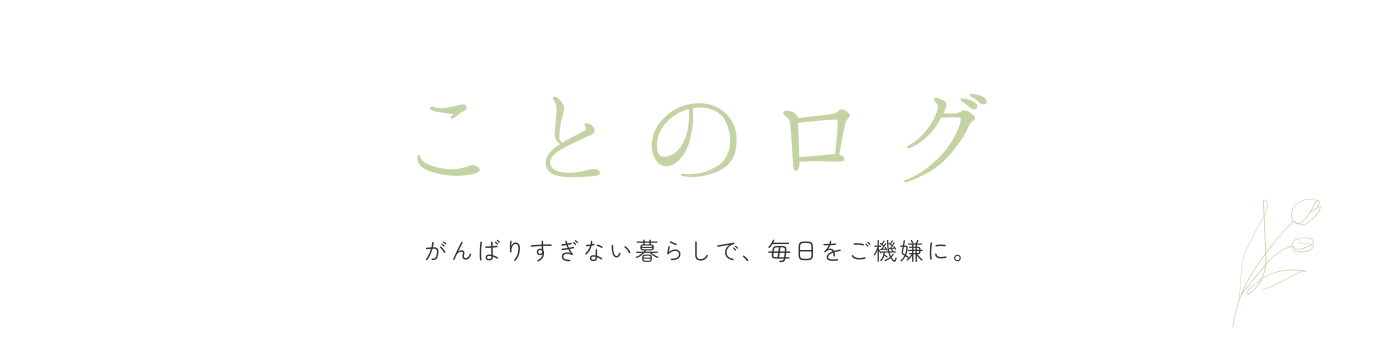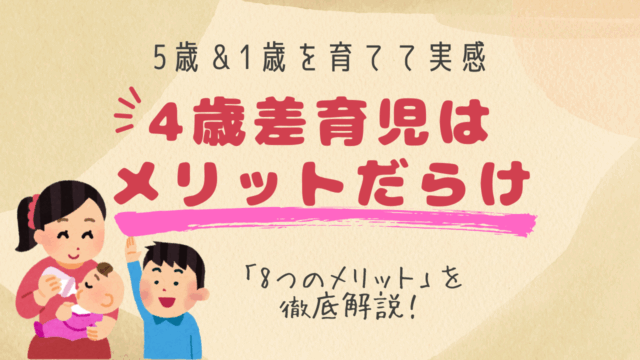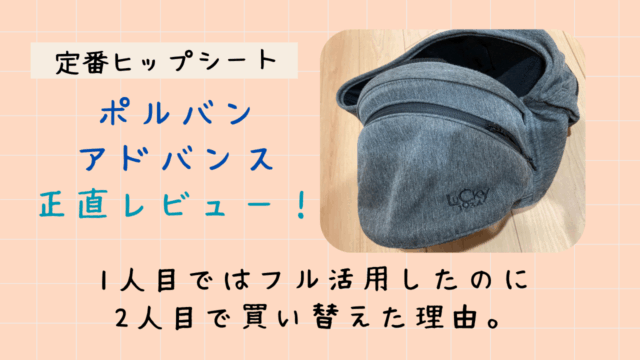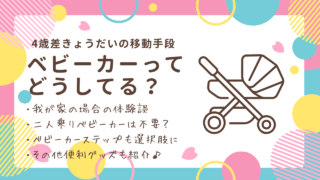4歳差育児のしんどい点とデメリット8つ。解決策も紹介【体験談】
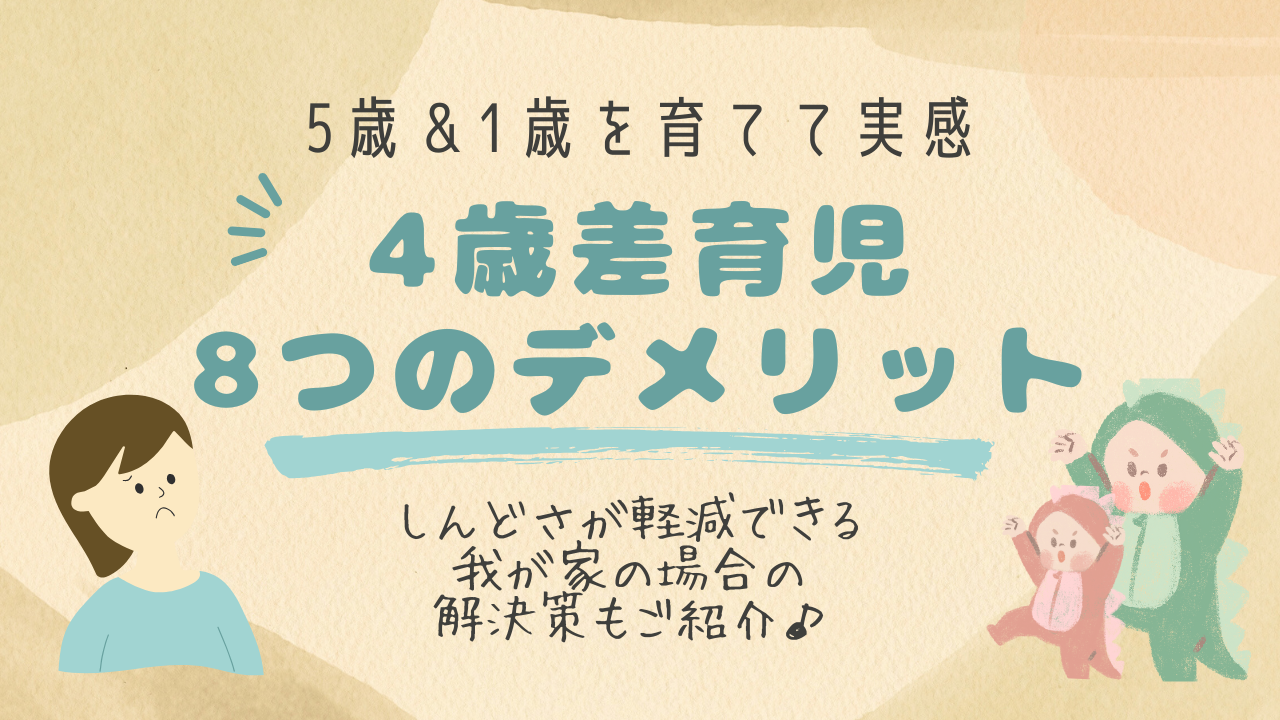
こんにちは!
5歳の男の子と1歳の女の子を育児中のことのです!
我が家の子供たちは、4歳差のきょうだいです。
4歳差って、比較的余裕を持って育児ができる年齢差だと思っていて、個人的にはすごくおすすめなんですよ。
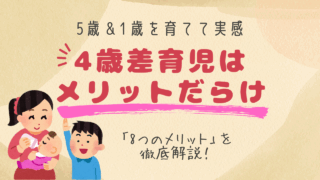
でも、メリットだけではなくて、4歳差ならではの、しんどい点やデメリットも存在します。
この記事では、実際に4歳差きょうだいを育てている私が実感している「4歳差育児のしんどい点やデメリット&デメリットについての我が家の対策」について書いていきます。
- 4歳差で出産予定/4歳差での妊娠を考えている方
- 4歳差育児特有のデメリットを知りたい方
- 4歳差育児特有のデメリットの対策法を知りたい方
4歳差育児のしんどい点とデメリット。この8つが大変!
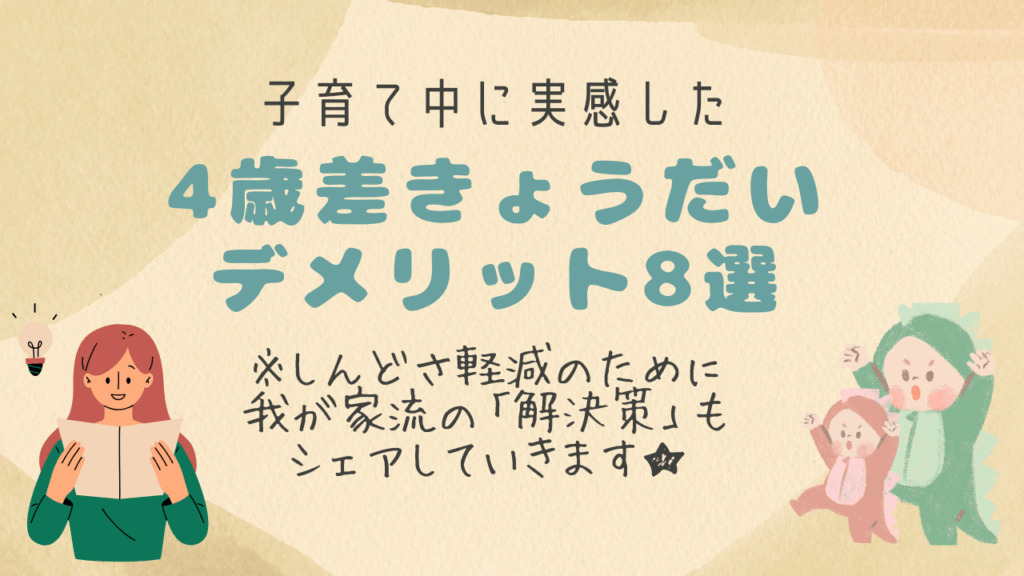 さて、ここからは4歳差きょうだいを育児中の私がリアルに感じている、「4歳差育児のしんどい点とデメリット」について書いていこうと思います。
さて、ここからは4歳差きょうだいを育児中の私がリアルに感じている、「4歳差育児のしんどい点とデメリット」について書いていこうと思います。
4歳差育児をしていて感じた、しんどい点やデメリットは8つあります。
デメリット解決策とともに、ひとつひとつ書いていきますね!
しんどいデメリット1:2人に合った遊び場を探すのが難しい
我が家の子供たちは5歳と1歳です。
年齢差があり、身体機能が違い過ぎるので、遊びに行くと以下のようなことがたびたび起こります。
- 5歳が満足するような公園の大型遊具。1歳には危ない
- 1歳がちょうどよく遊べる小さい遊具。5歳だと物足りない
- 5歳が楽しめそうな手作り工房。1歳は参加できない
- 1歳が安心して遊べる赤ちゃんスペース。5歳は入れない
【対策】遊び場探しは「考えすぎずにサクサク新規開拓!」
「遊び場探しが難しい」というしんどい点(デメリット)を解決するために、自分なりに考えていろいろやってみました。
- 「年が離れた2人ともが100%満足できる遊び場を探すのは難しすぎる」ということを頭に入れる
- 「まぁ少しは楽しめるかな~?」と思えたらOK!サクサク新規開拓しちゃう
最初は「2人とも100%楽しめるところがいい!」「行ってみて微妙だったら嫌だから絶対良さそうなところしか行きたくない!」とお出かけ先を吟味していた時期もありました。
そして、失敗を恐れた結果「結局行くのは同じところばかり…」というマンネリ状態に。
子供は良くても、親が飽きてきます。
お出かけ先のマンネリ化を防ぐには、新規開拓が必要です。
新規開拓のために「まぁ2人とも少しは遊べるかな~?」と思ったら、とりあえず行ってみよう」という感じにしました。
「とりあえず行ってみよう。微妙なら帰ろう。うちの子に合うかどうかは行ってみないとわからないよね」と考え方を変えることで、フットワークが軽くなり、お出かけ先の新規開拓ができるようにもなりました。
ローカルな遊び場の情報収集には、Instagramがおすすめです!
個人ブログの口コミやGoogleの口コミなどと併用して使っています。
- 「実際に子連れで行ってみた体験談」を聞ける
- 投稿者がたくさんいて情報も多く、検索カンタン
- 写真や動画が多く、視覚的にもわかりやすい
- 短くまとめられているので、パパや上の子とも情報共有しやすい
上の子に「ここに行こうと思ってるけど、どう?」と説明するときも、Instagramを見せながらと簡単だし、子供のテンションも上がります。
インスタってキラキラしててなんか苦手…と敬遠している方(私がそうでした)も、情報収集用のアカウントは持っておいても損はないかもしれません。
地方の遊び場情報も多いため、ローカルな遊び場を見つけられることもあります。
遊び場探しがぐっとラクになりました!
しんどいデメリット2:公園で下の子が上の子の真似をしたがり危ない
下の子は上の子の動きに興味津々。
我が家の下の子は、1歳後半になってある程度自由に動けるようになると、上の子の真似をはじめました。
- にーにみたいに、大きいジャングルジムにのぼりたい!小さいのは嫌!
- にーにみたいに、巨大滑り台の頂上まで行きたい!あそこから滑りたい!
- にーにみたいに、ぜんぶひとりでやりたい!ママ手伝わないで!
そんな感じの態度を出してくることも。
「危ないから登っちゃだめ!」「1歳にはまだ早いからだめ!」と一生懸命危険から遠ざけても、まぁいうことを聞きません。
結果、「登っちゃだめだよ!」「のる!!」「あっち!あっちの小さい滑り台で遊ぼう!」「いや!のる!!ままちがう!!」とお互い言い合うことになり…。
ただ子供の安全を確保したいだけなのに、疲れてしまいます。
【対策】公園で下の子がすぐ真似をするときは「割り切って付き添いを頑張る」
「公園で下の子が上の子の真似をしたがり危ない」というしんどい点(デメリット)を解決するために、自分なりに考えていろいろやってみました。
- 「上の子の真似をしたがるのは当然だよね。そしてダメって言っても聞かないよね」とある意味割り切る
- 親が付き添えばできそうなことなら、隣で補助しながらチャレンジ(本当に危ないことは止める)
最近気づいたのですが、我が家の場合は「真似したがるのは仕方ない」と親が割り切り、最初から協力してしまうのが一番スムーズのようです。
1歳や2歳といったら自分の体の動かし方がわかってきて、なんでも真似してみたい時期。
近くにはお兄ちゃんやお姉ちゃん。楽しそうな遊具に登って笑ってる…となれば、まぁ真似したくなる気持ちもわかります。
補助すればいけるな~と思ったら補助に徹します。
ますます目を離してはいけなくなり親は大変ですが「真似したいよね~そうだよね~じゃあ手伝うか~」くらいの軽い気持ちでいたほうが、案外しんどくない気はします!
公園に関しては、遊具が空いている場合(親が一緒に付き添って、小さい子がのんびりチャレンジしても迷惑にならないと感じた場合)のみ補助をしています。
人気の大きい公園は、空いていそうな曜日や時間帯を狙って行っています。混雑してきたらサッと撤退して別の場所に移動しています。
また、小さい公園については、すごく混んでいるところとすごく空いているところがあるので、なるべく空いている公園を選んでゆったりと利用しています。
しんどいデメリット3:2人分のおもちゃの管理が大変、誤飲の心配もある
子供に年齢差があると、遊ぶおもちゃも違ってくるので、おもちゃを置くだけでかなりのスペースが必要です。
さらに、上の子が4歳や5歳になると細かいおもちゃも増えてきます。
なんでも口に入れてしまう赤ちゃんがいると、上の子が愛用している細かいおもちゃは危ないですよね。
あとは私だけかもしれませんが、上の子が使う「UNO」「トランプ」「かるた」などのカードゲーム系も管理が地味に大変!

手の届く場所に置いておくと、下の子にばらまかれていたり、折られていたり、隙間に入れられて数枚足りなくなっていたりします…
きれいな折り紙なんかもそうです。
下の子の手の届く場所に折り紙を置き忘れると、全部中途半端にぐちゃぐちゃにされてしまいます。
そして「折り紙ぐちゃぐちゃになったぁ~~!」と泣き出す上の子…。
【対策】2人分のおもちゃの管理が大変なときは「分類してから整頓する」
「2人分のおもちゃの管理が大変、誤飲の心配もある」というしんどい点(デメリット)を解決するために、自分なりに考えていろいろやってみました。
- 子供たちが使うものを分類(子供だけで遊べるおもちゃ/親の手伝いが必要なおもちゃ/誤飲が怖いおもちゃ/カードゲーム類/工作用品)
- アイテムごとに置き場所を変えて管理
ある時、「おもちゃを分類してから移動して、それから整頓すれば少しはラクになるのでは…」と思って、おもちゃを分類してから、整頓しなおしてみました。
分類→移動→整頓することで、比較的マシな状態をキープできるようになりました!
- 子供だけで遊べるおもちゃ:リビングメインスペース
- 親の手伝いが必要なおもちゃ:2階子供部屋
- 誤飲が怖いおもちゃ:2階子供部屋
- カードゲーム類:リビングで親管理
- 工作用品:リビングで親管理
我が家の場合は上記のように分けています。
下の子については、誤飲の心配はもうほぼありませんが、念には念を入れて、遊ぶときにはしっかりと見守ります。
しんどいデメリット4:上の子の習い事選びが難しくなる
4歳差きょうだいだと、下の子が0歳のタイミングで上の子が4歳(年少)という計算です。
年少さんになると、習い事をはじめる子も増えてきますが、小さい子の習い事は親の付き添いが必須なところが多いと思います。
下の子を4歳差で産んでいると、赤ちゃんを連れて習い事の送迎や見学をすることになります。
私もやっていましたが、正直かなりせわしなくて、大変です!
- 下の子が退屈になりぐずる
- 下の子も一緒にやりたがって動き始める
- 下の子のおむつ替えなどでバタバタする
- 下の子の生活リズムを考えると、習い事をする時間帯が限られる
- 下の子の荷物が多いので地味に持ち歩きが大変
- 下の子を連れてきている人がほどんどいない場合、迷惑をかけないか不安になる
- 下の子が体調を崩した場合、上の子の習い事をお休みすることも
上の子のレッスンを見学しているのに、下の子の対応をしていたらよくわからないまま終わってしまっていたりします。
【対策】上の子の習い事選びは「お試し必須!土日の習い事や通信教育も検討」
「上の子の習い事選びが難しい」というしんどい点(デメリット)を解決するために、自分なりに考えていろいろやってみました。
- お試しレッスンで「周りの保護者の様子」「レッスン環境」などをチェック
- 土日に習い事を入れて、2人育児をパパと分担
- 家でマイペースにできる通信教育にも目を向けてみる
新しく習い事を始める前には、まずはお試しをしてしっかりと様子を見るのをおすすめします。
このとき上の子の様子を見るのはもちろん、下の子の様子、周りの保護者の様子、周りの保護者が下の子を連れてきているかなどもチェックしましょう。
ちなみに、我が家では「休日の習い事+通信教育」という形をとることにしました。
休日の午前に習い事(ヤマハ音楽教室)を入れて、パパと分担して育児しています。
上の子はママと一緒に習い事に参加、下の子はパパと2人で遊んだり近場でおでかけ、という分担制に。
(もともと、小さいうちは外での習い事はひとつまでと考えていたので、土日にできる習い事に変更しました)
それに加えて、「Z会の通信教育<幼児向け>」の通信教育も受講中。
「コツコツ学習習慣をつける」というよりは、「暇なときにまとめて解く」「暇なときに一緒に体験型教材をする」という感じでマイペースに使っていますが、勉強したことや体験したことは一応頭に入っているらしく、本人も楽しく取り組んでいるようです。
上の子は「こどもちゃれんじ」と「Z会」両方の経験があります。
最終的には上の子の好みでZ会になりましたが、どちらの教材もよく考えられていて、お勉強以外のことも学べるようになっていると感じました。
(2歳こどもちゃれんじ→年少Z会→年中こどもちゃれんじ~途中からZ会→年長Z会、と何度か変わっています)
「下の子がいるから、おうちでできる習い事を探している」という方には、通信教育もアリだと思います。
\どちらもおすすめです/
しんどいデメリット5:上の子の園の送り迎えが大変
4歳差きょうだいの場合は、上の子が年少になる年に下の子が産まれる計算になります。
上の子が通っている園は2階建てで、0~2歳児は1階で過ごし、3~5歳児(年少~年長)は2階で過ごすような感じになっています。
妊娠中に上の階へ…0歳を連れて抱っこで上の階へ…歩きたがる1歳を連れて上の階へ…地味に大変でした。
あと、基本的に車移動なので車で送迎するのですが、毎回車に下の子を乗せるのも大変でした。
【対策】送り迎えが大変なら「できればバス通園。ない場合はしょうがない!」
「上の子の園の送り迎えが大変」というしんどい点(デメリット)を解決するために、自分なりに考えて…みましたが…。
園バスがあり、バス通園が可能なら申し込もう!というくらいでしょうか(上の子の園はバスがありませんが…)
とくになし!(バス通園が可能なら利用するくらい)
このデメリットを避けたい場合は、園選びの段階で
- すべてのクラスが1階にある、平屋の園があれば検討
- バス通園ができる園を選ぶ
といいと思います。
「コニー抱っこ紐」を使うと、下の子の乗せおろしがちょっとラクになりました。車移動のママさんにおすすめです。
\車移動のママさんにとくにおすすめ/

しんどいデメリット6:上の子の「初めての園の行事」を見学できないかも
年少以降になると、「親参加のイベント」が増えてきます。
上の子が通っている園のイベントは少なめですが、それでも運動会や発表会はありました。
小規模保育園を卒園してからこども園に入ったので、まさに年少の運動会などは「初めての園の行事」でした。
しかし、4歳差きょうだいだと上の子が年少、下の子0歳の計算。
妊娠出産のタイミングや、下の子の月齢や様子によっては「上の子の初めての園のイベント」を見学できないこともあります。
また、スペースの関係などで、発表会を見学できる人数が決まっていることもあります。
上の子の園の場合もそうで、最初は「初めての発表会は、パパ・ママ・赤ちゃんで行って、泣いたら私と赤ちゃんだけさっと退出するでも良いかも」と考えていましたが、
上の子が通っている園では、発表会はひと家族で2人までの参加(抱っこ紐の中の赤ちゃんも1人にカウント)という決まりがありました。
「パパとママと赤ちゃんと3人で行こうかな…?」と考えている方は、まずは参加可能人数の確認をしておくといいと思います。
【対策】上の子の園行事は「園に詳細確認、パパと日程共有、一時保育検討」
「上の子の園行事に参加できないことがある」というしんどい点(デメリット)を解決するために、自分なりに考えてみました。
まず絶対避けたいのは「ママは下の子との対応をしないといけない。パパは仕事。上の子の園のイベント、誰も来れない…」という状態になることです。
- なるべく早めに、イベント概要(所要時間や家族ごとの人数制限)を園に確認
- 下の子を連れていきたい場合は、行ってもよさそうな雰囲気か確認
- ママが参加できなさそうな場合は、パパに休みを取ってもらい行ってもらう
- 下の子の月齢が大きくなってきていたら、一時保育やファミサポの利用を検討するのも◎
園からの「イベントのお便り」が来るのはけっこう近くなってからですが、プリントをもらう前でも、先に聞いておけば開始時間やおおよその終了時間を教えてもらうことができることもあります。
上の子のイベントに下の子を連れて行っていい雰囲気なら連れて行くのもありかなと思いますが、このあたりは園によるので先に確認しておくと安心です。
ある程度月齢が大きくなってきて、一時保育やファミサポ(ファミリーサポート)が使える場合は、検討してみるのもいいかもしれません。
イベント本番の前に数回、預けて練習をしておくと安心ですね。
(ちなみに、上の子のこども園では一時保育を実施していましたが「上の子のイベント参加のための一時保育は不可」とのことでした。上の子の園の一時保育に預けたい場合は、そのあたりも確認が必要だと思います)
しんどいデメリット7:きょうだいでのお揃いやリンクコーデが難しい
きょうだいでお揃いコーデやリンクコーデするのってすごくかわいいと思うんです。
でも、4歳離れていると「下の子ベビー服」「上の子キッズ服」という感じになってしまい、売り場が離れてしまいます。
そうすると、お揃いの服って本当に売っていないんです…。
上の子が110くらいまでならまだギリギリあったりしますが、120、130となると本当に探すのが難しい!
【対策】お揃い服は「自分で合わせてリンクコーデ風にする」
「きょうだいでのお揃いやリンクコーデが難しい」というしんどい点(デメリット)を解決するために、自分なりに考えてみました。
- 似たような服を探して「リンクコーデ風」を楽しむ
- メルカリでキーワード指定して探すと目当てのものが見つけやすい!
- サイズ展開が幅広いショップを探すようにすると見つかることも
お揃い服をいろいろ探して、見つけたら買うようにはしていますが、結局あまりないので…自分で合わせる方が早い!となりました。
我が家の場合は男女のきょうだいです。さらに顔立ちも好みも結構違うので、完全なお揃いではなく「リンクコーデ風」にしています。
お兄ちゃんはシンプルなワンポイントの青ボーダー、妹はアンパンマンのイラスト入りの赤ボーダー、などでもリンクコーデ感は出ます。
お兄ちゃんは半ズボンのオーバーオール、妹はジャンパースカートにするのもかわいい。
黄色の服、赤の服は男女どちらでも手に入りやすいので、色だけ合わせるのもかわいいなと思って時々着せています。
アプレレクールは80~140のサイズ展開のものが多いです。女の子向けが多いですが、たまに男女のきょうだいでもお揃いできそうなものもあります。

また、よく楽天のデビロックで子供のズボンを買うのですが、Tシャツのサイズ展開が90~160なので、兄弟はもちろん、カジュアルな感じなら兄妹、姉弟でも合わせることができそうです。

くすみカラーのお揃いならバースデイなどでもたまに見かけますね!
サイズ展開が幅広いショップを知っておくことで、ネットや店舗でもお揃いを探しやすくなりそうです♪
しんどいデメリット8:親が育児の知識をすっかり忘れている
下の子の子育てをするときは「1人目の時に学んだ育児知識をそのまま生かす」「1人目の時に編み出した育児のコツをそのまま応用する」ということができます。
ただ、上と下が4歳も離れていると、
- 年数が経ったので、当時覚えた育児の知識をすっかり忘れてしまった
- 年数が経ったので、1人目のときはどんな感じで育てていたかすっかり忘れてしまった
【対策】育児知識を忘れたなら「都度学びなおし」でも1人目よりはラク!
「親が育児の知識をすっかり忘れている」というしんどい(デメリット)点を解決するには、どうすればいいのか、考えてみました。が…
「学びなおしのチャンス」と思って学びなおすしかない!
解決方法…じゃないですね(笑)
まあ、そもそも上の子と下の子でいろいろ違うので、今までの育児の知識を覚えていたとしても、その知識が全部役に立つのかはわかりません。
私の場合は上の子は混合→完母育ち、下の子は混合→完ミ育ち。
母乳とミルクだと全然対応が違うので、その部分だけでもけっこう学びなおしました。
さらに、ほかの育児知識もほとんど忘れてしまっていたり、そもそも常識が変わっていたこともありました。
日々学びなおし。
ただ、めちゃくちゃ大変だったかというとそこまでそんなこともなく…
なんとなく感覚的に覚えていることもあったからか、1人目を4歳まで育てて自信がついたからか、1人目を育てるより2人目を育てる方が圧倒的に楽でした(精神的に)
まとめ:4歳差育児にもしんどい点とデメリットはあるけれど、考え方次第で解決!
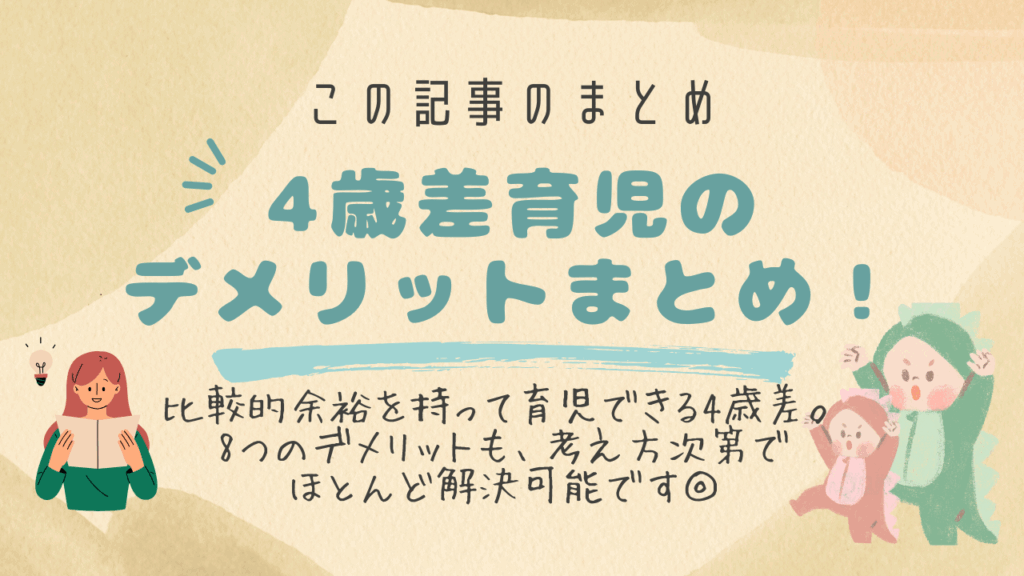 以上、「4歳差育児のしんどい点やデメリット&デメリットについての我が家の対策」という記事(体験談)をお届けしました。
以上、「4歳差育児のしんどい点やデメリット&デメリットについての我が家の対策」という記事(体験談)をお届けしました。
比較的余裕を持って子育てできる4歳差育児にも、やっぱり悩みやデメリットはあります。ただ、対策をしたり、親の考え方を変えることでなんとかなる気がします。
最後に簡単にしんどい点やデメリット&我が家の対策方法についてまとめておきます。
- 「2人に合った遊び場を探すのが難しい」→考えすぎずサクサク新規開拓がおすすめ
- 「公園で下の子が上の子の真似をしたがり危ない」→割り切って付き添いを頑張る方が案外ラク
- 「2人分のおもちゃの管理が大変、誤飲の心配」→分類してから整頓する
- 「上の子の習い事選びが難しい」→土日の習い事+通信教育に
- 「上の子の園の送り迎えが大変」→…しょうがない!(あれば園バス利用)
- 「上の子の初めての園行事が見学できない」→パパと相談!一時保育検討も◎
- 「お揃い服やリンクコーデが難しい」→自分で合わせる&サイズ展開豊富な店チェック
- 「親が育児の知識をすっかり忘れている」→気持ちを入れ替えて新しい知識を入れていく
こうまとめてみると、1~3は「上の子と下の子の発達に差があるからこその悩み」4~8は「上の子と下の子に年齢差があるからこその悩み」という感じですよね。
ちなみに…
ここまで4歳差育児のしんどい点やデメリットをあげてきましたが、別にデメリットだけってわけではありません。
上の子がある程度自立している状態から2人目育児をスタートできたり、上の子は下の子をかわいがってくれたり、ときどき育児の戦力になってくれたりするので、気持ちに余裕が出ておだやかに育児ができます!
デメリットもありますが、メリットや育てやすさの方が多く感じています♪
実際に育てて感じた、4歳差きょうだいのメリットについてはこちらの記事で詳しく書いているので、よろしければご覧ください!
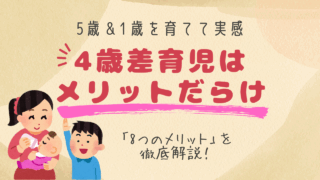
4歳差での妊娠を考えている方、4歳差で出産予定の方、同じように4歳差育児をしている方。これからも一緒に4歳差育児がんばりましょうね。
最後まで読んでいただきありがとうございました。この記事がどなたかの参考になればうれしいです!